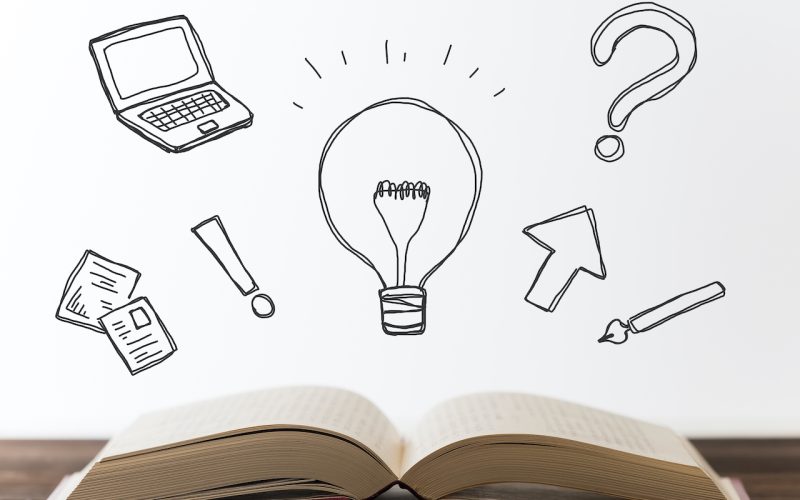近年、デジタル化が進む中で、販促ツールとしてのITの重要性は疑いようがありません。しかし、紙メディアにはITにはない独自の魅力も確かに存在すると考えています。
ITを活用した販促は、ターゲットを絞り込んで効率的に情報を届けることができます。
検索広告やSNS広告のように、ユーザーの興味関心に合わせてパーソナライズされた情報を届けることで、高いコンバージョン率を期待できるでしょう。自ら情報を探しに行くユーザーにとっては、必要な情報に素早くたどり着ける利便性は大きなメリットと言えます。
一方、紙メディアは「偶然の出会い」を生み出す力を持っています。
本屋さんで背表紙に惹かれて手に取った本が、自分の人生を変える一冊になることもあるように、意図せず目に入ったフリーペーパーやパンフレットから、新しいサービスやお店を知るきっかけが生まれることがあります。
これは、五感を刺激する紙の手触りや、物理的な空間を共有する紙メディアならではの体験と言えるでしょう。
デジタルが「効率」と「パーソナライズ」に優れているとすれば、紙は「偶発性」と「体験」に強みがあると言えます。偶発性と言いましたが、これは単なる偶然ではありません。戦略的に実行できることです。
偶発性を生み出すため、そして体験を創出するための戦略として、次のようなことが考えられます。
偶発性を生み出すための戦略
既存顧客へ新しい情報を届けられる:通販で常に同じ商品ばかり購入している顧客に対し、新たらしい商品や季節限定の商品、おすすめしたい商品などを積極的にアピールする会報誌を作り商品の発送とともに送る。コストをあまりかけずに行えるメリットもある。
情報量のコントロール:多くの情報を詰め込むのではなく、あえて興味を引くポイントだけに絞り込み、続きはWebサイトで、といった導線を作る。
ターゲットの広さ:デジタルが特定のターゲットに焦点を絞るのに対し、紙メディアは幅広い層にアプローチすることで、潜在顧客との「偶然の出会い」を生み出す。
デザインの工夫:目を引くデザインやキャッチーなコピーで、偶然手に取ってもらえる工夫をする。
体験を創出するための戦略
素材のこだわり:ざらざらした紙、光沢のある紙、厚みのある紙など、素材にこだわることで、触覚に訴えかける。
デザインの立体化:ポップアップカードや折り込み、型抜きなど、立体的なデザインで驚きや楽しさを提供する。
五感を刺激する:香りのついたインクを使ったり、特殊な加工を施したりして、視覚以外の感覚にも訴えかける。
物理的な行動を促す:応募券やクーポンを切り取って使う、スタンプラリーに参加するなど、紙ならではの物理的なアクションを組み込むことで、記憶に残る体験を創出する。
まとめ。紙メディアの特性を今一度見直し、ITとのメディアミックスで新たな境地を開こう
このように、紙メディアの特性を深く理解し、どのような「偶然」を、どのような「体験」として提供したいのかを明確にすることで、デジタルには真似できない独自の価値を生み出すことができます。
どちらか一方が優れているというより、それぞれの特性を理解し、目的に合わせて使い分けることが重要。
たとえば、新規顧客の開拓には紙メディアで幅広い層にアプローチし、既存顧客との関係構築にはITを使って詳細な情報を提供するといった戦略も考えられます。
デジタルと紙、それぞれの魅力を最大限に活かした販促戦略が、今後ますます重要になっていくと考えています。
紙メディアの特性を今一度見直し、ITとのメディアミックスで新たな境地を開きませんか?